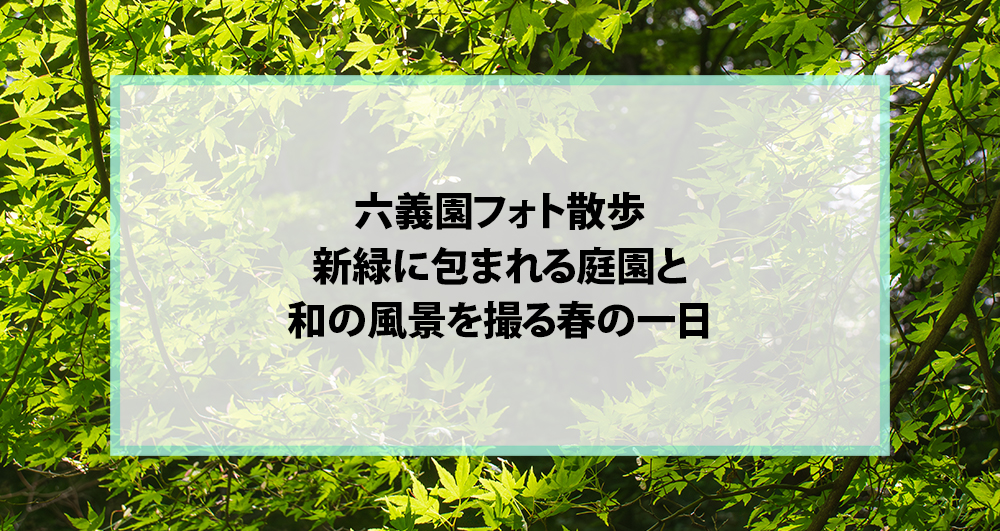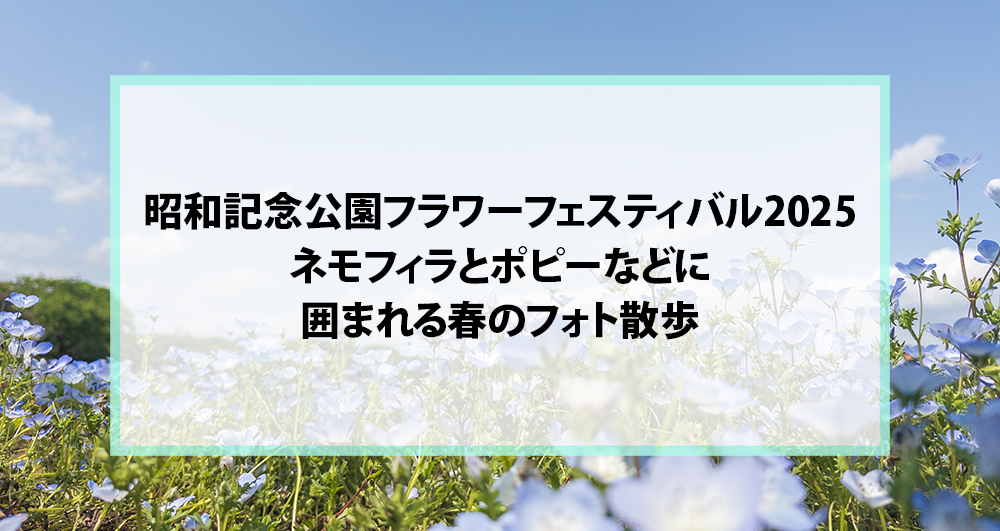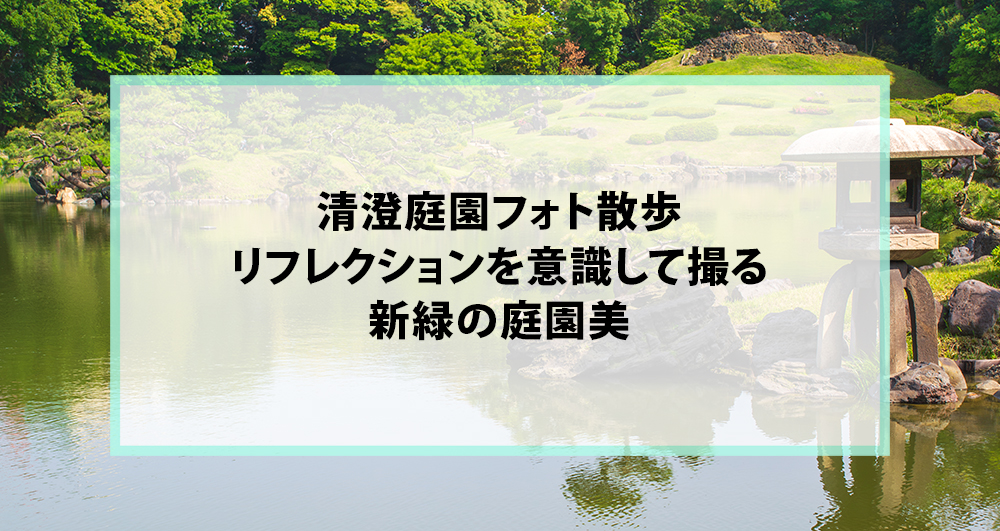この記事は「都内庭園フォト散歩シリーズ」の第1弾です。
⇒ 続編はこちら:「清澄庭園フォト散歩|リフレクションを意識して撮る新緑の庭園美」
都内にいながら、四季折々の自然を静かに楽しめる日本庭園「六義園(りくぎえん)」。
春のしだれ桜や秋の紅葉でも知られていますが、5月上旬の新緑の季節も鮮やかな緑の風景を撮影できる良い季節です。
今回のフォト散歩では、若葉があふれる園内を歩きながら、「緑の美しさ」と「和の情緒」を意識して撮影してきました。
池や茶屋、木漏れ日がつくる陰影の表現など、三脚なしでも構図の工夫も交えつつ、写真とともにご紹介します。
アクセス案内
- 所在地:東京都文京区本駒込六丁目
- アクセス方法:
JR山手線・東京メトロ南北線「駒込駅」より徒歩7分(正門)
都営三田線「千石駅」より徒歩10分(染井門から入園可・春のみ開門) - 開園時間:9:00〜17:00(最終入園は16:30まで)
- 休園日:年末年始(12月29日~1月1日)
- 入園料:
一般:300円
65歳以上:150円
小学生以下および都内在住・在学の中学生:無料
※上記は2025年5月時点の情報(変更の可能性あり。公式サイトでご確認ください)
六義園(東京都公園協会)公式サイト
六義園の概要紹介
六義園(りくぎえん)は、五代将軍・徳川綱吉の側近として知られる川越藩主・柳澤吉保によって、元禄15年(1702年)に築かれた大名庭園です。
和歌の趣を大切にした「回遊式築山泉水庭園」として知られ、園路を巡りながら池や築山の景色が次々と移り変わる、繊細で静かな美しさが魅力です。
園内には、紀州・和歌の浦をはじめ、和歌に詠まれた名所や中国の古典風景などが「八十八境」として表現されており、まるで詩の世界を歩くような体験ができます。
江戸時代を代表する大名庭園のひとつとして高く評価されており、明治時代には三菱財閥の創業者・岩崎彌太郎の別邸となりました。その後、昭和13年(1938年)に東京市へ寄贈され、昭和28年(1953年)には国の特別名勝にも指定されています。
新緑に包まれる庭園の景色
六義園の中心に広がる「大泉水」は、まわりを樹木に囲まれた静かな池。
訪れた日は天気にも恵まれ、空と緑が一面に広がる風景が印象的でした。
①妹山・背山 | 男女の情景を表現した築山の中島
池の中央に浮かぶ中の島には、「妹山・背山(いものやま・せのやま)」と呼ばれる二つの築山が築かれています。古来、“妹”は女性、“背”は男性を意味し、この島は男女の間柄を象徴する庭園表現のひとつ。大泉水を囲む松や草木が織りなす緑色の中、築山の存在感が印象的でした。

撮影した場所はこちら ▶︎ Googleマップで見る
②田鶴橋 | カーブを描く橋が描く構成美
大泉水に浮かぶ中の島へと架けられた「田鶴橋」。現在は通行不可のため渡ることはできませんが、その存在が庭園の構成美に深みを与えています。風の穏やかな時間には、水面に映る緑が橋を包み込み、まるで絵のような静寂の情景になるでしょう。

撮影した場所はこちら ▶︎ Googleマップで見る
③出汐湊 | 和歌の浦を模した静寂の水辺
六義園の南側に広がる「出汐湊(でしおのみなと)」は、紀州・和歌の浦の風景を模して造られたと伝わる場所。江戸の庭園美が今なお息づき、ビルのない静かな景観を楽しめる貴重な一角です。庭園を眺めるうえで最も重要な場所のひとつとされており、新緑の季節には水面に映る木々が、当時の景趣をより豊かに想像させてくれます。

撮影した場所はこちら ▶︎ Googleマップで見る
水面に映る新緑・囲まれた木々からの木漏れ日
六義園の中には、広い池以外にも木々に囲まれた静かな水辺や林の小径が点在しており、新緑の時期にはそれらが独特の美しさを見せてくれます。木々の間から差し込む光が、水面に淡く映り込み、光の反射や揺らぎが柔らかな雰囲気を引き立ててくれます。
④剡渓流 | 中国の古典に想を得た静寂の流れ
六義園八十八境のひとつ「剡渓流(せんけいりゅう)」。その名は、中国・浙江省にある山水の名勝「剡渓(せんけい)」に由来し、詩人・王羲之が舟遊びを楽しんだ故事をもとにしています。新緑の映り込む水面は、静けさと調和を象徴する景色として、庭園に静寂な風情を添えています。

撮影した場所はこちら ▶︎ Googleマップで見る
⑤山陰橋と蛛道 | 衣通姫の名を継ぐ道と時代を超えた橋
木製の「山陰橋(さんいんきょう)」は、明治から令和に至るまで幾度も架け替えられながらも、同じ意匠が受け継がれています。橋を渡った先に続くのが「蛛道(ちゅどう)」で、和歌の神のひとり・衣通姫(そとおりひめ)の歌にちなんだ名を持ちます。秋には紅葉が美しく映えるこの一帯は、季節の移ろいと共に雅を感じさせてくれます。

撮影した場所はこちら ▶︎ Googleマップで見る
⑥水香江 | 青もみじに包まれる静寂の癒し空間
江戸時代には清らかな水が湧き、夏には蓮の花が咲いていたと伝わる「水香江」。
今では青もみじの木陰が広がり、心地よい風が吹き抜ける静かなスポット。初夏の陽射しをやわらげてくれる、涼やかな緑のオアシスです。

撮影した場所はこちら ▶︎ Googleマップで見る
水香江付近の上を見上げると新緑の天井から差し込む光。木の枝も長く印象的でした。

撮影した場所はこちら ▶︎ Googleマップで見る
毎週更新で期間限定の無料素材も提供しています。
和の佇まいにふれる
六義園の見どころのひとつは、和の情緒を感じさせる木造の建築が、新緑とともに調和している点です。
⑦滝見茶屋 | 渓流と滝を眺める癒しの東屋
東屋の脇を清らかな渓流が流れ、岩の間から水しぶきをあげて滝となって落ちる「滝見茶屋」。
ここからは、流れ落ちる滝や石組「水分石(みずわけいし)」の景観を楽しむことができ、水音に耳を澄ませば、心がほどけていくような静寂のひとときが味わえます。新緑に包まれるこの季節、六義園の隠れた憩いの場です。

撮影した場所はこちら ▶︎ Googleマップで見る
⑧つつじ茶屋 | 古材と新緑に抱かれた高台の憩い処
つつじの古木材を用い、明治時代に建てられた茅葺き屋根の東屋。戦災をまぬがれ、六義園に現存する数少ない歴史的建築のひとつです。
築山の途中に位置し、他の場所とは異なる高さから園内の緑を見渡すことができます。木立に包まれたやや暗めの場所ですが、構図を工夫すれば、静けさをまとった落ち着いた一枚が撮れるスポットでもあります。

撮影した場所はこちら ▶︎ Googleマップで見る
緑陰に映える情景
⑨青もみじの間からのぞくフレーム風景
こうした自然の「フレーム」を意識すると、つつじ茶屋付近の同じ場所でも印象が変わった風景が撮れます。

撮影した場所はこちら ▶︎ Googleマップで見る
⑩青もみじ越しの視点から遠近感と季節感を表現
茶屋の全体を写すのではなく、一部だけを切り取って青もみじのモチーフと組み合わせることによって余韻のある構図になります。

撮影した場所はこちら ▶︎ Googleマップで見る
⑪青もみじに包まれているような石灯籠
石灯籠もまた、六義園の「和」を象徴する存在です。青もみじの中に溶け込むような配置で新緑とのコントラストが初夏の華やかさを感じさせてくれます。

撮影した場所はこちら ▶︎ Googleマップで見る
⑫花菖蒲の紫が鮮やかに彩る石灯籠
花菖蒲との組み合わせなど、場所によっては異なる表情を見せてくれます。

撮影した場所はこちら ▶︎ Googleマップで見る
季節の草花と出会う
六義園の魅力は新緑だけではありません。園内を歩いていると、足元や木陰に色とりどりの草花が咲いているのに気づきます。
5月の園内では、ツツジや花菖蒲、エゴノキ、小紫陽花などが見られ、落ち着いた緑の風景に彩りを添えてくれました。
⑬丘の斜面に咲き誇るツツジの群生
ピンク、白、赤のカラーが新緑の中に映え、園内を華やかに彩っていました。しかし、ツツジの咲くシーズンが終わる寸前だったため咲いている花をメインに藤代峠のツツジを少し引いて撮影しています。

撮影した場所はこちら ▶︎ Googleマップで見る
⑭細い枝から下がる白いエゴノキの花
小さな鈴のようなつぼみが印象的です。点光源があったので、光ボケもいれたかたちにしました。

撮影した場所はこちら ▶︎ Googleマップで見る
⑮淡い青色の小さな花が群れるコアジサイ
木陰で撮影したため、全体的に暗くなり、画像処理で明るくしています。

撮影した場所はこちら ▶︎ Googleマップで見る
こうした草花は、明るい日差しのもとでは撮りやすいものの、場所によっては木々が生い茂り、かなり暗い環境になる場面もありました。
撮影の工夫と気づき
今回の撮影では、自然な雰囲気を大切にしながら、明暗差のある園内でどのように撮るかを意識しました。
六義園は広い庭園である一方、木々が多く茂る場所も多く、光の状態は場所によって大きく異なります。
特に5月は葉が生い茂っており、場所によってはかなり暗く感じる場面もありました。
そうした状況でも雰囲気を損なわないように、撮影時には以下のような設定と工夫を行いました。
撮影時のカメラ設定について
- ISOは200までに抑えるようにして、ノイズをできるだけ少なく。
→ ISO400以上ではノイズが目立ちやすくなるため、極力低感度をキープ。 - F値はF5.6〜8あたりで絞り、全体のシャープさを保つ
- シャッター速度は1/100秒以上を目安に、手持ち撮影でもブレにくいよう工夫
Lightroomでの仕上げ
- 暗部を持ち上げて階調を調整(ハイライトとシャドウのバランスを調整)
- ノイズ除去は控えめに行い、ディテールをできるだけ保つ
- 全体の明るさを上げるよりも、部分的な調整ブラシを活用
暗さを活かす意識
すべてを明るく見せようとせず、「暗さが残る場所はそのままにする」判断もしました。
たとえば茶屋や林の中では、暗さそのものが“雰囲気”や“静けさ”を表現する要素になります。
後処理で明るさを均一にしすぎず、現地で感じた空気感を再現することを心がけました。
こうした設定の工夫と編集のバランスは、六義園のような光と影の豊かな場所では特に大切です。
その場の印象をどう写し取り、どのように伝えるかを考えながら撮影することが、ストックフォトとしても、記録写真としても説得力のある一枚につながります。
六義園のように三脚が使えない場所では、“現場での工夫”と“編集での調整”の組み合わせが大切です。
限られた条件の中でも、その場の空気感をうまく引き出すことができれば、写真は十分に魅力的になります。
本記事の写真はすべて、Adobe Lightroomで現像・編集を行っています。
明るさや色味を整えるだけで、印象がぐっと変わります。
Adobe Lightroom(公式サイト)はこちら。
まとめ | 新緑の六義園を歩いて感じたこと
初夏の六義園は、静かで落ち着いた時間が流れる癒しの空間でした。
新緑に包まれた池や茶屋、石灯籠のある風景は、日本庭園ならではの趣があり、撮影するたびに新たな構図や視点が見つかります。
三脚が使えないという制限はありましたが、十分に雰囲気のある写真を残すことができました。
これから訪れる方にとっても、撮影のヒントになれば幸いです。
紅葉など、別の季節にもまた訪れてみたいと感じる、そんな庭園でした。
※掲載写真についてはこちらをご覧ください。
※この記事にはアフィリエイトリンクが含まれます。リンクからのご購入で運営者に収益が発生することがありますが、読者の皆さまのご負担は一切ありません。